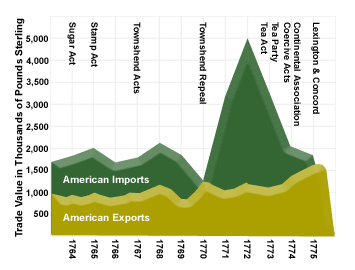1760年代半ばの不人気なグレンビル改革に始まり、10年間続いた不輸入協定やボイコットは、遠く離れたイギリスの政策立案者の注目を集めるためのアメリカの主要な手段でした。植民地の歳入増税策の批判者たちは、議会ではほとんど影響力がないことに気づきました。 アメリカ人がロンドンで有意義な意見を聞くためには、影響力のあるロビー団体からの支援が必要であり、それにはイギリスの商人や製造業者が適していた。 彼らの多くは、植民地との貿易関係や議会議員との関係を強く持っていた。ボイコットのように貿易が激減すれば、イギリスのビジネス界は経済的に打撃を受けることになる。 ボイコットのように貿易が激減すれば、イギリスの財界は経済的に打撃を受けることになり、政府を説得して政策を変更してもらうことが期待されました。
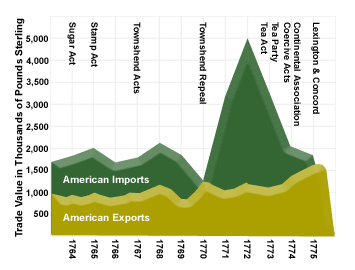
このような経済的報復は、砂糖法(1764年)に対しても行われましたが、スタンプ法の危機(1765年)やタウンゼント法(1767年~1770年)の後の騒乱の際に最大の成功を収めました。 1770年代前半は比較的穏やかな時期が続きましたが、強制法(1774年)の可決により突然の終焉を迎えました。 非輸入運動が最高潮に達したのは、第1回大陸会議で、イギリス製品の非輸入、非輸出、非消費を監督する機関であるアソシエーションの設立が決定されたときでした。イギリスの製造業者は、植民地の製造業の自給率が高まることを懸念していました。 トーマス・ゲージ将軍は、1768年にシェルバーン卿に宛てた手紙の中で、憂慮すべき状況を報告している。 “彼らは、期待されていた未開地の開拓をするどころか、ほとんどの場合、町に押し寄せて商売をし、母国から輸入すべき必需品で住民を助けている」多くのアメリカ商人は、熱狂的なボイコット支持者ではなかった。 彼らの生活は貿易に依存しており、その活動が途絶えることは経済的に深刻な影響をもたらすからである。 しかし、消極的な商人たちも、自由の子たちをはじめとする植民地の結束を強める者たちの説得により、しばしば賛同するようになりました。 アメリカ独立戦争の年表を見る